競馬初心者の方にとって、「未勝利」や「リステッド」といったクラスの用語は、「なんだかよく分からない…」と感じることがあるかもしれません。
この記事では、「競馬クラスのすべて」をテーマに、競馬におけるクラス分けの基本から詳しい解説までをわかりやすくお届けします。
まずは、中央競馬(JRA)のクラス構造について、新馬戦からリステッドクラス、さらには地方競馬のクラスまでを段階的に整理して解説します。
さらに、クラス分けを活用した馬券戦略についても初心者の方に向けて丁寧に説明し、どのクラスが馬券を買う際に注目すべきか、また逆に避けるべきクラスはどれかについても解説します。
この記事を通して、競馬の奥深い世界を一緒に探求していきましょう!
中央競馬のクラスとは?
ここでは、中央競馬(JRA)におけるクラス分けの仕組みと、その目的について分かりやすく解説します。
競馬におけるクラスとは、馬の実力や経験に基づいて分類されており、競走の公平性を保つために設けられた重要な仕組みです。
所属するクラスによって出走可能なレースが変わり、それぞれの馬に適した競走環境が提供されることで、競技全体のバランスが保たれています。
競馬のクラスはどう分けられる?
競走馬は、その年齢と勝利数に基づいてクラスが決定されます。
年齢については、2歳馬に関してはすべて2歳限定のレースとなります。
2歳馬はいくら強くても、3歳以上のレースに出走することはできませんし、3歳以上の馬が2歳戦に出走することはできません。
また、3歳馬は、原則として1月から5月までは3歳馬のレースしか出走できません。
それ以降は、「3歳以上」という条件のレースに出走することが可能です。
一方、勝利数については、一つ勝利するごとに、出走できるクラスが変わってくるという仕組みです。
元々は収得賞金によるクラス分けという形でしたが、2019年の夏季競馬より、幅広い人にもわかりやすくなるように、「勝利数」によるクラス分けがされています。
新馬から3勝クラスまで
競馬のクラスは、下記のように分けられます。
・新馬戦(メイクデビュー)
馬のデビューとなるレースが、この新馬戦です。
新馬戦は、2戦以上した馬、つまり出走経験のある馬の出走は許されておらず、ルーキー馬同士の争いとなります。
この新馬戦を勝利した馬は「1勝クラス」に上がります。
・未勝利
このクラスは、新馬戦で敗退した馬たちのレースです。
新馬戦で2着が何度あっても、1勝のクラスには上がれず、未勝利戦で勝利するまで戦わなければなりません。
また、初出走の馬がこのクラスに出走することも可能です。
未勝利レースに勝てば、新馬戦で勝った馬と同じように、1勝のクラスに上がることができます。
・1勝クラス~3勝クラス
1勝クラス、2勝クラス、3勝クラスは、その名の通り、何勝しているかどうかで決まるクラスです。
1勝のクラスの馬が2勝のクラスに出走することはできますが、2勝のクラスが1勝のクラスのレースに出走することはできません。
それは、オープン馬が3勝のクラスに出走できないといったように、どのクラスにも適用されます。
公平性の担保から、強い馬が下のクラスに出走するといったような、弱いものいじめのようなことはできないのです。
オープン以上のクラス 新設のリステッド(L)とは?
3勝クラスまでは「条件戦」と呼ばれるクラスです。
その条件戦をクリアすれば、オープン入り、つまりより賞金の高いレースへの出走が可能となります。
・オープン特別
条件戦をクリアした馬同士の争いの中で、重賞ではないレースです。
一応エリートの集まるレースとなりますが、年齢や実力もバラバラであることもしばしばあります。
・リステッド(L)競争
最近新設された競争です。
オープン特別の中でも少し格の高い、重賞以下、オープン特別以上の競争という位置づけのレースです。
・G3
このG3以上がいわゆる「重賞レース」となります。
勝てば「重賞馬」となり、賞金も4000万を超えてきます。
・G2
中央競馬(JRA)の中でG1の次に上位に位置するクラスです。
賞金が7000万円近くなることから、若手騎手がプレッシャーに押しつぶされて人気馬を飛ばすことも続出します。
・G1
中央競馬(JRA)の中で一番上位のクラスです
G1の中でも、日本ダービーや有馬記念など別格のレースがありますが、G1を勝利した牡馬はほぼ種牡馬入りすることができるなど、G1勝利の重みは別格です。
地方競馬のクラスとは?
これまでは中央競馬(JRA)のクラスについて解説してきましたが、地方競馬のクラスシステムは中央競馬とは大きく異なります。
地方競馬では、主催する地域ごとに独自の規則やシステムが存在しており、その仕組みは非常に多様です。
ここでは、中央競馬との違いに加え、地方競馬ならではのクラス分けの特徴や詳細について分かりやすくご紹介します。
中央競馬との違い
中央競馬(JRA)では、年齢と勝利数によってクラスが分けられており、初心者にも比較的分かりやすい仕組みとなっています。
一方、地方競馬では、「B2-二」などの表記が用いられ、一見すると分かりづらい印象を受けるかもしれません。
地方競馬のクラス分けは、基本的に「アルファベット」と「数字」の組み合わせで構成されています。アルファベットはクラスの強さを示しており、Aが最も強く、Dが最も弱いクラスです。このアルファベットに加え、数字でさらに細かく分類されています。
たとえば、南関東競馬(大井競馬、浦和競馬、川崎競馬、船橋競馬)の場合、統一されたクラス体系は以下の通りです:
(強い)A1 > A2 >> B1 > B2 > B3 >> C1 > C2 > C3(弱い)
さらに、レースのスケジュールにもこのクラス分けが反映されています。一般的に、C3クラスのレースは早い時間に行われ、メインレースとしてA1クラスが設定されるという形です。
このように、地方競馬特有のクラス分けは独自性が強く、各競馬場ごとの特色も楽しむポイントの一つとなっています。
各主催者による違い
地方競馬のクラス分けは、地域ごとに異なる細かなルールや段階が設定されているのが特徴です。
例えば、兵庫県の園田・姫路競馬では、A1からC3までの7段階に分かれています。また、一部地域ではクラス分けにポイント制を採用しているほか、中央競馬(JRA)では廃止された降級制度が残っているなど、独自の仕組みを維持しているケースもあります。
さらに、地方競馬独特の特徴として、クラス内でさらに細分化された「組」という概念があります。
具体的には、同じクラスでも細かいグループに分けられており、それが漢数字やカタカナで表されます。たとえば、漢数字の場合は「一」が最も強く、カタカナの場合は「ア」が最も強いといった具合です。
例えば、「A2-二」という表記であれば、A2クラスの中でも「二組」に属する馬が出走するレースを指します。このような仕組みにより、クラスが細分化され、同じ実力レベルの馬同士が競う公平なレースが行われています。
地方競馬のクラス分けは、中央競馬(JRA)に比べてやや複雑ですが、このシステムを理解することで、より一層地方競馬を楽しむことができるでしょう。
競馬のクラスを利用した馬券の買い方
競馬では、クラスによってレースの性質や難易度が大きく異なります。
また、クラスが上がるにつれて得られる情報量や、その活用の難しさも変化します。例えば、未勝利戦で頻繁に勝利している騎手が、G2以上のレースでは全く結果を残せないといったことも珍しくありません。
そこで、競馬初心者にとってどのクラスが馬券購入に適しているのかを、分かりやすくご紹介します。
競馬初心者におすすめのクラス
競馬初心者におすすめのクラスは、ズバリ、オープンのG3以上、とりわけG1クラスです。
その理由は大きく2つあります。「盛り上がり」と「情報量」の多さです。
初心者が競馬の醍醐味を味わうなら、G1レースの熱狂を体験するのが最適です。G1レースは、競馬ファンやメディアの注目が集まり、会場やテレビ中継も一段と盛り上がります。その熱気を感じることで、競馬の魅力にぐっと引き込まれるでしょう。
さらに、G1レースは出走馬や騎手に関する情報が豊富です。注目騎手としては、ルメール騎手や川田騎手、モレイラ騎手、ムーア騎手などが挙げられます。これらの一流騎手が騎乗する馬は、好成績を収める可能性が高いため、馬券を当てやすくなります。特にG1レースでは「良い騎手が良い馬に乗る」というシンプルな構図が成り立ちやすく、予想を立てる際のヒントになります。
一方で、条件戦や未勝利戦は若手騎手が台頭するケースも多く、予想が難しくなることがあります。その点、G1レースは初心者でもわかりやすい競馬の楽しさを感じられるクラスと言えます。
競馬の熱狂と勝利の喜びを味わうなら、まずはG1レースを体験してみてはいかがでしょうか。
競馬初心者におすすめできないクラス
競馬サイトの中には、「オープンクラスやリステッド(L)クラスは初心者には推奨しません」という意見もあります。確かに、ギャンブルの観点から見れば、少し難易度が高いかもしれません。
しかし、競馬初心者に一番おすすめできないクラスは、新馬戦です。
その理由は、新馬戦に出走する馬はすべて未知の存在だからです。もちろん、生産牧場(例えばノーザンファーム)や調教師(矢作調教師や手塚調教師など)、騎手(ルメール騎手や川田騎手)が関わっていることで人気が集まることがあります。これらの要素は競馬ファンにとって大きな注目ポイントですが、それでも、出走経験のない馬同士の戦いとなるため、予測が非常に難しく、未知の部分が多く残ります。
新馬戦は、いくら人気があっても、初めて競馬を楽しもうとする初心者には不安要素が多く、ギャンブルとしての安定感に欠けるため、初心者にはあまりおすすめできません。
競馬を楽しみ、勝つためには、まずは経験のある馬同士の戦いが見られるレースを選ぶことが、予想を立てるうえで重要となります。
まとめ:競馬の楽しみ方を初心者向けに解説
この記事では、中央競馬(JRA)と地方競馬のクラスについて解説しました。
「中央競馬(JRA)のクラスは知っていたけれど、地方競馬のクラスは知らなかった…」という方も多かったかもしれません。
地方競馬のクラスは一見複雑に感じるかもしれませんが、一度仕組みを理解すれば、実はとてもシンプルです。
初心者の方には、新馬戦に無闇に手を出さず、まずは情報が豊富で予測しやすいレースに注目することをおすすめします。
もちろん、「3勝クラスのダート短距離競走を極めた」といった独自の楽しみ方を見つけるのも良いでしょう。
中央競馬(JRA)と地方競馬のクラスの仕組みをしっかりと理解し、自分に最適なクラスのレースを見つけて、より深く競馬を楽しんでください。
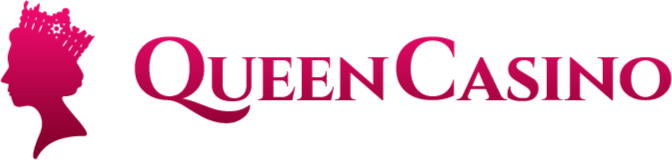

コメント